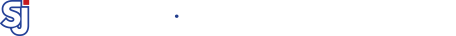
平素より格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。 誠に勝手ながらソフトウェアジョブズは2023年9月29日をもって、サービスを停止し、Webサイトを閉鎖いたしました。
これまで利用いただきました皆さまには、心より御礼申し上げます。
【会員の皆さまへ】ご利用の際にご登録いただいた個人情報は、現在、案件に従事いただいている方を除き、Web サイト閉鎖とともに全て消去させていただきます。
改めましてこれまでのご愛顧、誠にありがとうございました。
【本件に関するお問い合わせ先】こちらの問い合わせフォームをご利用ください。
■問い合わせ先
バルテス株式会社 人材開発担当